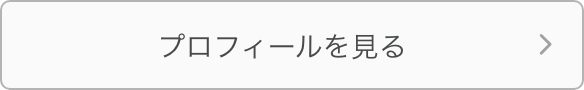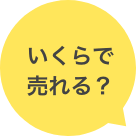共有名義の不動産を売却する際に「トラブルになりやすい」と、聞いたことがある人も多いでしょう。共有不動産は通常のものと違い、実際に多くのトラブルが発生しています。
共有名義の不動産をトラブルなく売却するには、売却する方法やトラブル事例を理解しておくことが大切です。
本記事では、共有名義の不動産を売却する方法や流れ、トラブル事例について解説します。記事の後半では、共有名義の不動産売却のトラブル対処法を紹介しますので、問題を起こさずに売りたい人はぜひ参考にしてください。
この記事の目次
不動産の共有持分とは
そもそも共有持分とは、不動産を複数人で所有し、それぞれがもつ所有権の割合です。
3人で不動産を所有し、所有権を均等に分ければそれぞれの共有持分は1/3です。また、3人で分けたとしても均等である必要はなく、ひとりの持分を1/2、ほか2人の持分を1/4とすることもできます。
ただし、完全に共有持分を操作できるわけではなく、購入する際には購入代金を払った割合になります。たとえば、3,000万円の物件を購入する際にAが2,000万円払ってBが1,000万円払った場合、共有持分はAが2/3、Bが1/3となるわけです。
また、共有持分に応じ、次のように不動産を扱える行動に制限がかかります。
|
共有持分 |
例 |
|
|
保存行為 |
共有者単独で実行可能 |
建物や敷地の管理 |
|
管理行為 |
共有持分の過半数の同意が必要 |
賃貸契約の締結 |
|
変更行為 |
共有者全員の承諾が必要 |
不動産の売却 |
共有名義の不動産を所有する際には、制限の内容を把握し不動産を使う必要があります。
共有名義の不動産を売却する方法5選
共有名義の不動産を売却する方法は、次の5つです。
-
共有者全員の承諾を得て不動産売却する
-
共有持分を共有者に売却する
-
共有持分を不動産会社に買取ってもらう
-
土地を共有持分に応じて分けて売る
-
共有物分割請求を起こす
共有不動産は通常の不動産と異なり簡単に売れないため、どのような方法で売却できるのか覚えておきましょう。
1.共有者全員の承諾を得て不動産売却する
共有者全員から売却の承諾を得れば、共有名義の不動産を売却できます。
共有名義の不動産売却は変更行為に該当し、共有者全員の承諾が必要です。全員の承諾を取得して売却した場合、売却代金は共有持分に応じて分配します。また、売却諸費用も共有持分に応じ、それぞれの共有者が支払います。
ただし、共有者のひとりでも売却に反対すると、共有名義の不動産は売れないため事前の根回ししておくといいでしょう。
2.共有持分を共有者に売却する
共有持分なら単独の意思で売れるため、ほかの共有者に売却するといいでしょう。
不動産自体を売却するのは変更行為に該当しますが、共有持分は自分ひとりの権利であるためほかの共有者の承諾がいりません。
共有持分が増えれば不動産を自由に使いやすくなるため、共有者が購入者の候補になります。
3.共有持分を不動産会社に買取ってもらう
共有持分を購入してくれる共有者がいない場合、不動産会社に買取ってもらうのも方法のひとつです。
不動産会社はビジネスにつながると判断すれば、共有持分も購入してくれます。不動産買取なら、購入者を探すことなくすぐに現金化できます。
ただし、買取は相場よりも売却金額が低くなるのには注意しましょう。
4.土地を共有持分に応じて分けて売る
共有不動産が土地なら、共有持分に応じて分筆し売却する方法があります。
分筆とは、登記でひとつの土地になっているものを、複数に分割する手続きです。登記上で土地を分割したら、その分割の内容にしたがって現地に境界標を設置します。
単独名義になるよう土地を分割すれば、単独の意思で売却できるようになります。
ただし、土地を分筆するには土地家屋調査士に確定測量を依頼し、法務局で手続きしなければなりません。これらの手続きをするには、数十万円の費用がかかります。
5.共有物分割請求を起こす
共有物分割請求を起こせば、共有持分をほかの共有者に購入してもらえる可能性があります。
共有物分割請求とは、裁判所を通じて共有名義を解消するための申し立てです。申し立てした場合、まずは共有者同士で共有状態をどう解消するか話し合います。話し合いが決裂したら、訴訟を提起し裁判所の判決に従って共有状態を解消します。
あくまで話し合いと裁判所の判断となるため、必ず共有持分を購入してもらえるとは限りません。場合によっては、全員の同意をもって不動産を売却したり、ほかの共有者の共有持分を購入したりといった方法を取るほうがいいと判断されるケースもあります。
共有名義の不動産を売却する流れ
共有名義の不動産を売却するときは、次の流れに沿って進めます。
Step1.共有者全員から売却の承諾を取得する
Step2.不動産売買の代表者を決める
Step3.費用の負担割合を決定する
Step4.不動産売買契約を締結する
売却するまで手続きが多いため、どのような手順が必要なのか理解しておきましょう。
Step1.共有者全員から売却の承諾を取得する
共有名義の不動産を売却する場合、まず共有者全員から承諾を取得しなければなりません。
承諾は口頭でも構いませんが、意思を統一するためにも書面で取得しておくといいでしょう。書面を取得しておかないと、のちのちトラブルになるおそれがあります。
Step2.不動産売買の代表者を決める
共有者全員から売却の承諾を取得したら、不動産売買の代表者を決めます。
代表となった共有者は、不動産会社との窓口になってさまざまなやり取りを進めます。たとえば、代表者が不動産会社から売却に必要な書類を聞き、それぞれの共有者に伝えるといったやり取りです。
また、共有者全員で集まるのが難しい場合、代表者に対しての委任状を作成すれば売買契約や引渡しを一任できます。
Step3.費用の負担割合を決定する
共有名義の不動産を売却する際、各共有者は原則的に共有持分に応じた費用を負担します。
ただし、費用負担は話し合いで自由に変更できるため、共有持分と違う金額を払うのであれば負担する割合を決めます。
Step4.不動産売買契約を締結する
販売活動を開始し、買主を発見したら不動産売買契約を締結します。
共有不動産を売却する際には、不動産売買契約書に共有者全員が記名押印しなければなりません。しかし、共有者が印鑑証明書つきの委任状を発行している場合は、受任者がほかの人を代表して契約できます。
Step5.確定申告する
売買契約を締結した後は、不動産を引渡して確定申告までおこないます。
確定申告は共有者がそれぞれ、個別に全員がおこなわなければなりません。不動産を売却して譲渡所得税が発生する場合、共有者は自分の分だけ納税する仕組みです。また、譲渡所得税の減税を受ける制度を申請する場合も、確定申告時に個別申請する必要があります。
共有名義の不動産売却に必要な書類
共有名義の不動産を売却する場合、共有者はそれぞれ次の書類を準備する必要があります。
|
書類名 |
取得場所など |
備考 |
|
権利証 |
本人所有 |
登記済証や登記原因証明情報ともいいます |
|
印鑑証明書 |
住民登録している自治体 |
発行から3ヶ月以内のものが必要です |
|
実印 |
本人所有 |
実印登録されている印鑑 |
|
本人確認書類 |
本人所有 |
運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど |
|
固定資産税決定通知書 |
本人所有 |
毎年4月ごろに自宅に郵送されてくる書類です。 |
|
住民票 |
住民登録している自治体 |
登記簿の所有者と本人の所有者の住所や氏名が一致しない場合に必要です |
|
委任状 |
自作 |
代表者に不動産売買を任せる場合 印鑑証明書の添付と実印の押印も必要 |
上記の書類は一般的な書類であり、売却する物件や売主によって必要なものが変わります。不動産売買を実際におこなう際には、不動産会社に必要な書類をご確認ください。
共有名義の不動産売却で起きがちなトラブル
共有名義の不動産売却で起きがちなトラブルは、次のとおりです。
-
売却に同意してくれない
-
贈与税が課税された
-
買取業者が共有物分割請求した
-
相続で共有持分が複雑になった
トラブルの内容を理解し、問題が起きないように売却していきましょう。
売却に同意してくれない
不動産の売却に同意してくれない場合、共有者どうしでトラブルになります。
共有名義の不動産を売りたい人には、売却したいと思う理由があります。しかし、共有者ひとりでも売却に反対すると、目的を達成できません。
とくにお金がないのを理由に売りたいと思っている人がいる場合、売却できないと生活に影響する可能性が高く大きなトラブルになってしまいます。
共有者から売却の同意を取り付けるのは難しいため、日頃から共有者どうしで売却について話し合っておくといいでしょう。共有者の意思を常に確認すれば、同意を取得しやすくなります。
贈与税が課税された
共有名義の不動産は、親族が共有者となっている場合が多く安く売ってしまいがちです。しかし、相場よりも低い金額で売ってしまうと、相場と売却金額の差額を贈与としてみなされます。
贈与とみなされた部分には、贈与税が課税されるため注意しましょう。贈与税には年間110万円の基礎控除が認められているため、差額が基礎控除を超えると贈与税の課税対象になります。
親族に共有持分を売却する際には相場を調べ、贈与税が課税されない金額で売り渡す必要があります。
買取業者が共有物分割請求した
共有持分を買取りしてもらった場合、買取業者が共有物分割請求するケースもあります。
買取業者は利益を上げるために、買取りした共有持分を共有者に売却したり、ほかの共有持分を購入したりします。しかし、共有者によっては共有持分の売却にも、購入にも対応しない人もいるでしょう。
このような場合、買取業者は利益を出すために、共有物分割請求を起こします。
共有者は共有物分割請求を起こされると、民法により共有解消の打ち合わせに必ず参加しなければなりません。共有持分を売買する気がない共有者にとって迷惑な話であり、共有持分を買取業者に売った人に対して文句をいう人もいます。
買取業者に共有持分を買取りしてもらう前には、共有者に相談するべきでしょう。買取業者に売却するデメリットを伝えておけば、共有物分割請求を起こされても心の準備ができます。
相続で共有持分が複雑になった
共有名義の不動産を所有しているときに相続が発生すると、共有者が増え、よりいっそう利用しにくくなります。
たとえば、共有者3人のうちひとりが死亡し、法定相続人が4人いた場合、共有者の数が6人になります。6人の意思を統一するのは難しく、不動産売却するのは困難です。
共有者が高齢で相続が発生しそうな場合、早めに不動産を処分するといった対応することが大切です。
共有名義の不動産売却トラブル対処法
共有名義の不動産売却で起きがちなトラブルの対処法は、次のとおりです。
-
共有名義にならないよう相続する
-
共有者と定期的に処分について話す
-
共有持分を売却する際には共有者に相談する
共有不動産の売却トラブルには対処法があり、きちんと対策すればトラブルを防げます。
共有名義にならないよう相続する
共有名義にならないよう相続すれば、トラブルの発生を防げます。
たとえば、3,000万円の価値がある不動産と3,000万円の現金を2人で相続するなら、ひとりが不動産、もうひとりが現金を相続します。
このように相続すれば、単独名義で不動産を所有できるため共有トラブルは起きません。
共有者と定期的に処分について話す
共有者と定期的に処分について話せば、お互いの意思が確認できます。
処分に反対する人がいる場合、誰がどのように不動産を管理するのか、相続が発生したときの取り扱いはどうするのか話し合いましょう。共有名義のデメリットを共有しておけば、売却を検討する材料になるかもしれません。
共有持分を売却する際には共有者に相談する
共有持分は単独の意思で売却できますが、売るときにはまず共有者に相談しましょう。
買取業者に買取りを依頼すれば、共有持分をすぐに売却できるかもしれません。しかし、共有者の中には共有持分を買いたい人、買取業者が買取りするデメリットを知らない人もいます。
勝手に売却すると、このような人は感情的になってしまいます。共有者どうしの関係を壊さないよう、あらかじめ相談してから売却しましょう。
まとめ
共有名義の不動産を売却するには、共有者全員の同意が必要です。
全員から承諾が取れない場合、共有持分の売却を検討するといいでしょう。共有持分は自分の意思で売却できる権利であり、共有者の許可は必要ありません。
しかし、勝手に売却するとトラブルを発生させる可能性もあるため、事前に共有者に相談してから進めましょう。
共有者どうしのトラブルを避けるには、定期的な話し合いをしてお互いの意思を確認しておくべきです。共有者の考えが理解できれば、トラブル防止になり、処分や管理もしやすくなります。