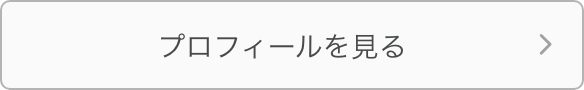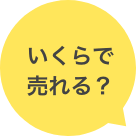「売却前に土地の価格を知りたい」「土地を相続する予定だがどれくらいの価値があるか調べたい」など、土地の価格を自分でも調べたいという場合もあります。
土地の価格にはいくつかの種類がありますが、それぞれ目的が異なります。土地の時価を知るためにはどの価格を参考にすればよいか、どのように調べればよいか分からない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、自分で調べられる価格はあくまでも目安です。売却したい、正確な価格を知る必要がある場合、不動産会社の査定などが必要です。
この記事は、自分で時価を調べる方法、不動産会社に査定を依頼するときの注意点について解説します。
この記事の目次
土地の時価とは実勢価格のこと
土地の時価は「実勢価格」と同じといえます。
実勢価格とは、不動産市場において、実際に取引されている価格です。実勢価格は、取引時の経済環境や市場動向の影響も受けるため、土地の時価と一緒と考えてよいでしょう。
実勢価格を調べる方法
実勢価格を調べる方法として、「不動産ライブラリ」や「レインズ・マーケット・インフォメーション」があります。それぞれについて解説します。
不動産ライブラリ
国土交通省の「不動産ライブラリ」は、不動産の過去の成約情報や防災情報、都市計画情報などを地域ごとに調べられるサイトです。
3か月(四半期)ごとにデータがとりまとめられており、住所や最寄り駅からの距離、土地の形状、前面道路の幅員などの条件を設定して、検索することができます。
条件が近い土地があれば、㎡単価(1㎡あたりの土地価格)に土地面積を乗じることで、およその価格を知ることができます。
レインズ・マーケット・インフォメーション
レインズ・マーケット・インフォメーションは、不動産流通機構が運営する不動産情報システム「レインズ」の成約情報を調べられるサイトです。
さまざまな検索条件を設定して価格を調べられます。ただし、レインズの成約情報は、国土交通省の不動産ライブラリの「成約価格情報」にも反映されています。
複数の価格から土地の時価を調べることもできる
土地には、「実勢価格」のほか、「公示地価」「固定資産税評価額」「相続税評価額」とその目的に応じていくつの価格があります。
不動産ライブラリで過去の成約情報を調べたものの、条件が近い取引が見つからない場合は、これらの価格から土地の時価を計算することもできます。
次章以降、それぞれについて時価の計算方法を解説します。
公示地価から土地の時価を調べる方法
まずは公示地価から土地の時価を調べる方法について解説します。
公示地価とは?
公示地価は、市場の土地取引の指標あるいは不動産鑑定の規準として、国土交通省が毎年1月1日時点の価格を3月に公示するものです。
令和6年においては、都市部とその周辺の標準地26,000地点が対象となっています。標準地とは、条件が極端に良い、あるいは悪い土地ではない標準的な土地です。
また、国ではなく各都道府県が公表する価格に「基準地価」があります。毎年7月1日時点の基準地1㎡の価格を、9月下旬頃に公表します。目的は公示地価と同じですが、公示地価のような都市部とその周辺といった制限はなく、公示地価を補完する役割といえるでしょう。
公示地価の調べ方
公示地価は、先に紹介した「不動産ライブラリ」で調べられます。
地図上や一覧表で標準地を検索し、調べたい土地の条件と類似する取引情報があれば、その取引価格を参考とすることが可能です。また、過去の地価情報も登録されているため、地価が上昇もしくは下降傾向などを知ることもできます。
公示地価から土地の時価を計算する方法
公示地価から実勢価格の目安を知る方法は次のとおりです。
実勢価格=公示地価(基準地価を含む)×1.1×土地面積
ただし、1.1倍という指標は、地域によって変わります。都市部や土地の需要が高い地域では、公示地価よりもっと高い水準で取引されることもありますし、土地の個別要因によって異なります。
固定資産税評価額から土地の時価を調べる方法
固定資産税評価額から土地の時価を調べる方法は以下のとおりです。
固定資産税評価額とは?
固定資産税評価額は、固定資産税や登録免許税の税額を算出するときに基準となる価額です。1月1日時点の評価額を、国が定めた固定資産評価基準をもとに各市町村(東京都は都)が定め公表します。
3年に1度固定資産税評価額の見直しが行われるため、そのタイミングで評価額が変わります。建物は築年の経過とともに価値が下がる減価償却資産である一方、土地は減価償却しない資産です。そのため、土地の評価額は、地価上昇によって上がる場合もあります。
なお、固定資産税評価額と間違えやすいものに課税標準額があります。課税標準額は、固定資産税評価額に住宅特例などを考慮して計算された価格です。最終的に課税標準額に税率を乗じて固定資産税額を算出します。
固定資産税評価額の調べ方
固定資産税評価額は、毎年4~6月頃に市区町村から送られてくる納税通知書のなかの課税明細書で確認できます。登記上の住所や面積とあわせて「価格(評価額)」が記載されていますので確認してみましょう。
また、複数の所有者で共有する土地の場合、納税通知者は代表者にのみ送られてきます。そういった場合には、各市区市町村で作成・保管されている固定資産課税台帳で確認することも可能です。
固定資産税評価額から土地の時価を計算する方法
固定資産税評価額は、およそ公示地価の70%の水準になるように調整されています。
・公示地価=固定資産税評価額÷0.7×土地面積
そのため、土地の時価(実勢価格)は公示地価の1.1倍が目安となるため、固定資産税評価額から土地の時価を計算する方法は次のようになります。
・土地の時価=固定資産税評価額÷0.7×1.1×土地面積
相続税評価額から土地の時価を調べる方法
次に、相続税評価額から土地の時価を調べる方法です。
相続税評価額とは?
相続税評価額は、相続税や贈与税を計算するときに基準となる価格です。税金の申告時に納税者と税務署が基準となる評価額をもとにスムーズに申告できるように公表されています。
道路(路線)に面する1㎡あたりの価格で表示されていることから「路線価」ともいわれます。
相続税評価額の調べ方
相続税評価額の調べ方には、地域に応じて「路線価方式」と「倍率方式」があります。
路線価方式
路線価方式は、毎年7月1日に、不動産鑑定士の評価や公示価格、売買事例などをもとに、国税庁や各市区町村が決定し発表される評価額です。
路線価は、国税庁の「路線価図・評価倍率表」で調べることができます。
例えば、下図は東京都杉並区の路線価図の一部です。赤丸の道路に面する土地1㎡あたりの価格は「340D」となっています。
路線価は、1,000円単位で表記されているため、この土地の評価額は、304,000円/㎡です。例えば、100㎡の土地の場合、相続税評価額は「304,000円/㎡×100㎡=30,400,000円」となります。
また、評価額は土地の形状や道路に面する間口、奥行などによっても変わります。土地の形状によっては、奥行価格補正率など各種補正率が適用され、評価額が変わります。
なお、「D」は借地権割合といい、その土地の権利に借地がどれくらい割合を占めるかを示すものです。つまり、その土地を貸した場合の価格を評価するもので、この土地(借地権割合がD)の場合、60%となります。
出典:国税庁:「路線価図・評価倍率表」
倍率方式
路線価は、都市部や市街地では路線価が定められている一方、郊外地域や農村部などでは定められていません。倍率方式は、路線価が定められていない地域の土地の相続税評価額を算出する際に用いられます。
倍率方式では、その土地の固定資産税評価額に指定された倍率を乗じて計算します。
倍率は、路線価方式と同様に、国税庁の「路線価図・評価倍率表」で調べることが可能です。
例えば、固定資産税評価額が2,000万円の土地で指定されてる倍率が1.1倍であれば、2,000万円×1.1=2,200万円が相続税評価額となります。
相続税評価額から土地の時価を計算する方法
相続税評価額は、およそ公示地価の80%に定められます。
・公示地価=相続税評価額÷0.8×土地面積
そのため、土地の時価を計算すると次のようになります。
・土地の時価=相続税評価額÷0.8×1.1×土地面積
なお、土地の価格を調べる意味では、suumo(スーモ)などの不動産ポータルサイトで調べることも考えられます。条件が近い土地の売り出し情報を検索し、1㎡あたりの価格を調べられます。
ただし、ポータルサイトの価格は、売り出し価格であり成約価格ではありません。取引に応じて、売り出し価格から価格変更や値引き交渉などを経て成約価格が決まる点には注意してください。
正確な土地の時価を知るには不動産会社の査定が必要
ここまで土地の時価を計算する方法を解説しましたが、実勢価格や固定資産税評価額などから計算する価格は、目安として考える必要があります。
周辺環境や道路づけなどその土地の個別要因すべてが考慮されているわけではないため、正確な土地の時価を知るには、不動産会社の査定が必要です。
簡易査定と訪問査定
不動産会社の査定方法には、簡易査定と訪問査定があります。
簡易査定は、机上査定ともいい、不動産の面積や築年数などの基本情報と過去の取引事例や公示地価をもとに査定する方法です。
実際に現地に足を運んで査定するわけではなく、結果もすぐに分かるため、手間や時間をかけたくない、およその金額を知りたいだけという場合は活用しやすいでしょう。
不動産会社の担当者でなく、AIが情報と取引データをもとに査定するAI査定も簡易査定の1つといえます。
一方、訪問査定は、実際に現地を見て、周辺環境や道路との接道状況などを調査し査定する方法です。土地の境界やインフラの引き込みがどのようになっているか、隣接する土地の状況や周辺の建物など、価格に影響する条件すべてについて調査します。
一般的な訪問査定では、1~2時間程度の調査を実施し、3日~1週間程度で査定結果が出ます。簡易査定と比べ、日程調整の手間や時間はかかりますが、高い精度の査定価格を知ることが可能です。
不動産会社に査定を依頼するときの注意点
不動産会社に査定を依頼するときには注意しなければならない点もあります。
自分でも相場を調べておく
いくつか不動産の価格を知る方法をご紹介しましたが、自分でも相場を調べておくことが大切です。
不動産を売却するとき、売り出し価格は不動産会社の査定価格をもとに決めます。このとき、相場を調べておくことで、不動産会社の提示する査定価格に対して適正な判断をしやすくなり、高すぎる、あるいは安すぎる売り出し価格になるリスクを減らせます。
また、自分で相場を調べることで、どういった条件が土地の価格に影響するのかを知ることができます。不動産会社から査定価格の根拠を聞くときに理解しやすいでしょう。
複数の不動産会社に依頼する
不動産の査定は、複数の不動産会社に依頼しましょう。なぜなら、複数の査定価格やその算出根拠を比較できるからです。
不動産の査定結果が不動産会社によって異なることは珍しくありません。土地や一戸建てはマンション以上に査定価格に差が出やすい傾向もあります。
これは、土地の形状や道路付け、周辺環境すべてが物件ごとに異なり、査定する会社によって評価が異なりやすいためです。
査定価格は売り出し価格の基準となるため、1社の査定価格だけに依存してしまうと、それが違った場合、なかなか売れない、あるいは反対に売却価格が安すぎたという可能性があります。
また、複数社に依頼することで、査定価格だけでなく、不動産会社や担当者の実績や経験、販売方法なども比べることができ、依頼先を選びやすくなります。
どの不動産会社に依頼すればよいか分からない場合は、1度に複数社に査定を依頼できる「不動産一括査定サイト」を利用してもよいでしょう。
まとめ
土地の時価は実勢価格と言ってよく、国土交通省のサイトで調べられます。ただし、過去の取引事例がすべて登録されているわけではなく、特に、土地取引が少ないエリアなどは、条件に近い成約事例を見つけることが難しい場合もあります。
その場合、固定資産税評価額や相続税評価額から時価を算出することも可能です。ただし、自分で調べられる価格はあくまでも目安です。
売却する場合は、不動産会社に訪問査定を依頼し現地で査定してもらうことが必要になります。このとき、複数の不動産会社に査定を依頼することがポイントです。
査定価格や価格の根拠を比較してもっとも信頼性が高いと判断した会社に依頼しましょう。そのとき、不動産会社の売却エリアでの実績や販売方法、担当者との相性などもしっかり確認して決めましょう。